地域共生社会の実現に向けて
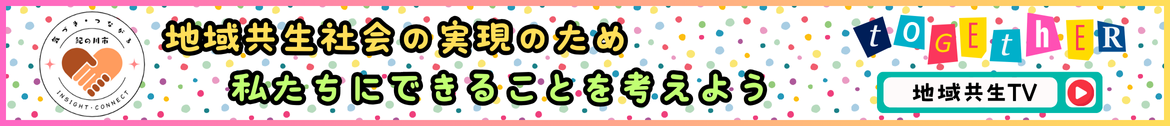
地域共生社会とは「支え手側」「受け手側」というこれまでの固定された役割分担意識を超え、住民が地域の課題を我が事として捉え、地域の関係団体等とつながりながら支え合う地域社会のことです。紀の川市において、市民の交流促進や総合相談体制の検討など、まち全体で支え合うことのできる仕組みづくりを進めていきます。
地域共生社会の実現に向けた取り組み
少子高齢化、核家族化及び地域、親族とのつながりの希薄化により、世帯の抱える問題も複合化、複雑化しています。 例えば、高齢の親と長年ひきこもって仕事をしていない子の世帯や親の介護と子育てを同時に行っている世帯、知的や精神に障害があり就労や家計管理が出来ず生活に困窮している世帯など単独の制度だけでは解決できず、「生きづらさ」を抱えながら生活を送る方が増加しています。
「生きづらさ」とは
生きづらさとは、それぞれの日常生活や人間関係によってその抱える不安や悩みはさまざまですが、社会的適応が難しいことや感情のコントロールが難しいこと、自分の価値観や感覚が周囲と相違があることなどから悩み、何かを決断することも困難となる状態のことを言うのではないかと考えます。
また、その要因もさまざまで、「経済的不安」「自己否定感」「こころの不調や病気、障害」などがあげられます。 できれば、その生きづらさを誰かに相談してほしいですが、困難な場合もあると思います。そんな時は、誰かが「気づき」、相談機関等に「つなぐ」ことが大切です。できるだけ早期に気づくことも重要です。
早期に「気づき、つなぐ」
地域には、民生委員(児童委員)や社会福祉協議会、相談支援事業所があり、もちろん市役所にも相談窓口を設置し、多様な相談が受けられる体制を整えています。さまざまな相談に対応できるよう、専門職も配置しています。
「相談しましょう」と言われても動き出しが容易にできない方も多い印象です。自身で決断ができずに悩まれている方も多いのではないでしょうか。紀の川市では、下記のように情報配信や相談体制の充実に向け、取り組みを進めています。大切な人生ですので、相談しながらいきませんか。
取り組み事例の紹介
地域共生に関する情報配信
紀の川市公式YouTube内で「地域共生TV」と題し、地域共生観点から各課の制度や民間相談機関等の紹介をしています。

福祉部内の連携強化
福祉部内の各課の情報共有や重層的な支援の実施のため、連絡調整会議を実施しています。多様化、複雑化する家庭の課題に対し、各課が連携して対応できる仕組みについても話し合っています。また、自殺対策担当課と連携し、職員向け研修も実施しています。
相談体制の充実 ※行政の取組み
行政としても、多様化する市民ニーズに対し、今までの縦割りの制度による支援ではなく、多機関・他分野の関係機関が横串を刺した連携で、重層的かつ包括的に支援する体制構築の取組みの推進が必要となっています。
紀の川市でも令和5年3月に第3次地域福祉計画が策定され、子どもや高齢、障害などの分野や制度の枠を超え、多様化した課題やニーズに対して包括的に取り組む地域共生社会の実現をめざすとしており、市民の交流促進や総合相談体制の検討など、まち全体で支え合うことができる仕組みづくりを進めることとなっています。まち全体で支え合う仕組みづくりのために、市民同士が「気づき」、そして、「つなぐ」ことが大切です。
つなぎ先は、市役所であることも多く、まずは、市職員も同様に市民と対話した際に、「気づいた」ときは、他課に「つなぐ」仕組みが必要であるのではないかと考え、窓口に来られた悩みを抱える市民の声に「気づき」、「丸ごと受け止め」、「専門機関につなぎ」、「見守る」を包括的に支援するための連携強化ツールとして「つなぐシート」を全庁的に配置しています。

つなぐシート・つなぎ先シートの活用
つなぐシート
自殺対策担当課と連携し、自殺予防対策で活用されている「つなぐシート」を地域共生観点からも運用しています。つなぐシートは、主な来庁目的以外にも生きづらさを相談された場合に、担当課へつなぐ際、書面をもってつなごうという取組みです。どこに相談したらよいかわからない、相談に行くことを迷っているなどに対し、市役所全体で生きづらさにアプローチしていきます。
つなぎ先シート
相談内容によっては、市役所以外の相談機関の紹介を必要とする場合があります。このような場合も、できるだけつなぐことができるよう、県内の主な相談機関の一覧「つなぎ先シート」を各課に配布しています。広く、多面的に生きづらさに対応できる仕組みづくりに取り組んでいます。
活用の流れ

リンク
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511

